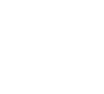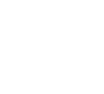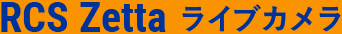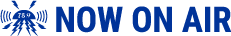2025-2-27 木
SSF Explorer 第48回 2月27日OA(池子の森のお話)
今日のSSF Explorerは「池子の森のお話」池子の森自然環境調査会の山浦安曇さんにお話を伺いました。
テーマ「池子の森に春を見つけに行こう」
毎日寒い日が続いています。早朝の池子の森では池も凍っていて、キンキンに冷えていますが確実に春に近づいています。今日は春の見つけ方についてお話しします。
1.カエルの産卵はじまる
①池子の森にはどんなカエルがいるの?
池子の森には、4種類のカエル(アズマヒキガエル、ウシガエル、モリアオガエル、ヤマアカガエル)が生息しています。そのうち、ヤマアカガエルというカエルは今まさにこの寒い時期に(まだ他の種類のカエルが冬眠している2月に)冬眠から目覚めて、水辺に卵を産みにきます。
えっ!こんなに寒いのにもう卵産んじゃうの?と思う方もいるかもしれません。実はヤマアカガエルが卵を産むタイミングというのがあって、それは、1月下旬から2月の間で、まだ気温が低いんだけど、少しだけ気温が上がって雨が降ったときです。
(ヤマアカガエルは、オスは4~6cm、メスは4~8cmくらい。林や草地の中で冬眠しているのですが、卵を産むときだけ水辺に集まってきます。水辺に集まってきたオスたちは、夜になるとメスを呼ぶ合唱を始めます。)
今年は2月に入って雨が降った日は何日があるんですが、2月12日に雨が降ったので、もしやと思い早朝に見に行きました。産んでいました!
池のほとりで耳を澄ませていると、ヤマアカガエルのオスがメスを呼ぶ声が聞こえてきました。それはこんな声です(キュルキュル→と鳴き声も聞かせてくださいました)。
確認のため水辺に近づくと、ちょうど産み落とされたばかりの新鮮な卵の塊が見つかりました!やったーという気分です。
その前日には卵や鳴き声は確認していないので、まさにその瞬間に立ち会えたわけです。
カエルが冬眠から目覚める日は気温や湿度が多いに関係しているのですが、その自然の情報をカエルと共有している感があって、とても満ち足りた気持ちになります。(自分も生き物のなかまであることを実感することができる嬉しい瞬間です)
お腹に卵が入っているメスがやってくると、オスたちはメスに飛びつきます。1匹のメスに何匹ものオスが飛びつきます。でも、メスはなかなか卵を産んでくれません。メスに飛びついた数匹のオスガエルたちはしばらくすると、1匹、また1匹と離れていきます。そうして最後に残ったオスだけがメスと一緒に卵を産むことができるのです。生み出された卵のかたまり(卵塊といいます)は水を吸って直径15~25cmくらいに膨らみます。一つの卵塊には1500~3000個の卵が入っています。
卵は、約2週間でオタマジャクシになります。水の中の植物や小さな動物などを食べて育ちますが、食べ物が少ない場所では共食いもします。いろいろなものを食べながら大きくなり、他の多くの種類のカエルが卵を産む5月の初め頃になると、アカガエルのオタマジャクシは小さなカエルになって、やがて親ガエルたちのいる林や草地に旅立って行きます。


②ヤマアカガエルはどうしてわざわざ寒い時期に産卵するの?
不思議ですよね。だって2月ってまだ雪が降る日もあるでしょうし、氷が張る日だってあります。他の種類のカエルはもう少し暖かくなってから産卵します。
実は、アカガエルはそもそも北方起源のカエルで、卵の胚が暑さに弱いのです。北方系のカエルなので、水温が高いと卵がかえらないんですね。他のカエルよりも一足先に産卵することによっていいことがあります。寒い時期には天敵となるヘビがまだ冬眠から目覚めていないってことです。また、オタマジャクシの天敵となる水生昆虫がいないため、敵の少ない状況でぐんと成長できるから、と言うメリットもあるんですね。
③繁殖行動した後の親ガエルは、寒い中、どう過ごすの?
繁殖行動したあとの親ガエルも、まだ寒いのでもう一度冬眠に入ります。「二度寝」するんです。私たちもよくやりますよね。
アカガエルは、寒さで死ぬリスクを負ってでも、敵を避ける生存戦略を選んだというわけです。また、寒さで死ぬリスクを少しでもなくすため、アカガエルのなかまは繁殖期間がとても短いのです。短ければ、繁殖期間に雪が降ったり、気温が急に低下したりするリスクに遭う確率が少しでも減るからです。
一方で、アマガエルやトノサマガエルなど、夏に繁殖するカエルは、そのようなリスクが無いので、わりとダラダラと長い期間、繁殖活動をしています。
④カエルの調査はどのように行っているの?
環境省が行っている「モニタリング1000里地調査」という全国規模の生物調査プロジェクトに参加しているのですが、その手法にのっとって調査しています。
アカガエル類の卵塊は、約 1,500 個の卵が1つの塊になったものです。年1回の産卵期には、 産卵可能なサイズの全てのメスが1匹あたり1つの卵塊を産卵します。そのため、全ての卵塊の数を数えることでその地域に生息するアカガエルの個体数を確実に把握しています。毎年、2月から4月ぐらいにかけて、水辺を回りながら産み落とされた卵の塊の数をカウントしていきます。
⑤カエルを調べるのはどうして?
アカガエルの仲間は、春先に産卵してオタマジャクシからカエルに変態した後は、水田の周辺の森林の林縁部や林内で生活をしています。そのためアカガエルの生育には、冬でも水が枯れることのない水辺やカエルの移動を遮ることのない水路、夏でも気温や湿度が安定した十分な広さの森林…というように、水辺と森という対照的な環境が連続して存在していることが大切。陸と水の両方に生息することから、環境の変化を敏感に感知する指標生物としても知られています。アカガエル類の卵塊数を調査することで、地域のアカガエル類の生息状況を長期的にモニタリングし、水辺や森のそれぞれの広さやそれらのつながりを評価できるのです。
2.ウグイスの初鳴き
もうひとつ春の訪れを感じさせてくれる子がいます。それはウグイスです。
実は冬でもウグイスは鳴いています。笹藪の下の方からチャッチャッという声がするのを聞いたことがありませんか。それはウグイスです。「私はここにいるよ」というくらいの軽い鳴き交わしです。ところが繁殖期になるとおなじみのホーホケキョという鳴き声に変わるんです。ホーホケキョは、オスがメスに求愛するときやなわばりを主張するときの鳴き声(さえずり)です。4月になればホーホケキョはよく聞くことができますが、実はこのホーホケキョの初鳴きが2月ごろなのです。かなり早いですよね。
ちなみに昨年は、1月16日にホーホケキョを確認しています。今年はまだです。もう明日には鳴き始めるかもしれません。
この番組を聴いてくださっているリスナーさんだけにとっておきの池子の森情報を紹介します。
池子の森には「ウグイスカグラ」という植物があるのですが、この植物は、ちょうどウグイスがホーホケキョと鳴き出すことに合わせたかのように花を咲かせます。
淡い紅色の可憐な花で、小さなハンドベルのように下向きに咲きます。この時期、花をつけている植物は他にないので、ひときわ目を引きます。花の時期は短くあっという間なのでぜひ見つけてください。ウグイスがタイミングよく鳴いていたら最高ですよ!


3.イベント情報
・3月8日(土)冬の早朝探鳥会 池子の森自然環境調査会がご案内します。
申し込みは終了しています。探鳥会は次は5月頃を予定しています。
・4月13日(日)春の植物観察会 池子の森自然環境調査会がご案内します。
「広報ずし3月号」で案内予定。
・月イチガイドツアー 毎月第一日曜日の10:00~12:00、簡易案内所にて。予約不要、参加費無料。ガイドが案内所で待機しています。お声がけいただいた方に対し、1組につき15分程度の公園紹介(生きものや歴史、写真映えするスポット、景観、ほか雑談)
この機会に池子の森に詳しくなってみませんか?