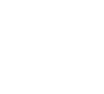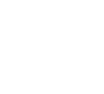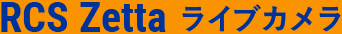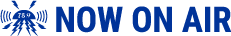2025-4-18 金
SSF Explorer 第55回 4月18日(星空リビング)
昨日、4月17日は、春の土用の入りでした。土用というと、夏の「土用の丑の日」を思い出すコトでしょう。子どものころ、土曜日ではないのに、そして、牛の日なのに鰻を食べる。不思議でした。
土用とはいったなんなのか?
「土用」は「土旺用事」のこと。土旺用事(どおうようじ)とは「土が旺盛に働き支配する」という意味。
土用が生まれた理由には五行説(ごぎょうせつ)という古代中国で生まれた思想が関係しています。これは、この世のあらゆるものは全てが木火土金水の五つの要素の組み合わせで成り立つという考えです。五行説はただ物質だけの成り立ちを説明するだけでなく、色や味、星々、そして季節まで全てをこの五種類のもの、あるいは性質の組み合わせで説明しようとしました。
季節、そう四季まで五行で説明しようとしたのです。ではどのように考えたかというと、
春→木 春は木(植物)が盛んに伸びる季節。
夏→火 夏は火のように暑い季節。
秋→金 秋は金属のように冷えてゆく季節。
冬→水 冬は水のように冷えきって停滞する季節、
では、土は?
土の性質は全ての季節に均等に存在する、と考えることにして、各季節の最後の18~19日を「土用」としました。土用が季節のあいだに入れられたのも、五行説では「土用」には季節の交代を円滑に進めるという意味があると考えられているからです。土には、死んだものを「土に還す」性質と「命を育成する」二つの性質が兼ね備えられており、異なる季節の間に「土用」を置くことで、消滅する古い季節と、まだ充分に成長していない新しい季節の性質が静かに交代して行くと考えられたからです。
春の土用は、立夏の前日までなので4月17日から5月4日までということになります。
良く聞く話しに、土用の期間は「土公神(どくじん)」という神様が支配する期間なので 土をいじること、掘り返すこと、井戸掘りすることなどを行っては禍が起こるというもの。そうはいっても、仕事で土を掘り返さないと行けないこともあります。そこで、救いの神のような、土用の間日(まび)というものがあります。
これは、文殊菩薩様が土用の期間のうちの数日、土公神一族を天上の清涼山に集めて下さって、この数日間は地上に土公神様がいらっしゃらなくなるので土を動かしても祟りを受けないという日です。季節毎に決まりがあって、例えば春の土用は日にちの干支が「巳、午、酉」今年の春なら、4月18日、19日、22日、30日、5月1日、4日。5月5日は立夏ですので、この6日間になります。気になる方は、この日なら、庭仕事や家庭菜園なんかもやりたい放題!(笑)
今年は、土星の環の消失が3回あります。
最初は、3月24日でした。でもこれは太陽に近すぎて土星が見られませんでした。
土星の環が見えなくなるのはどういうことなのか?
星の環は、厚みが100メートルほどというたいへん薄いので、地球から見て真横方向になるとほとんど見えなくなります。もうひとつは、太陽に対して、傾いて回っている土星ですが、その太陽に対して真横方向になると、環に光が当たらないので反射しません。つまり見えない。地球も太陽に対して、傾いて公転してますよね?で、もう一つは、土星の環の太陽が当たっていない側に地球がある、という状態。
3月24日の消失は、地球から見て土星の環が真横になった状態。そして、この日から5月7日まで太陽の光が当たっていない側から土星の環を見ていることになります。それでも、この状態の土星を見ようと思ったら、早起きが必要ですし太陽に近いと見えないので5月3日から7日の早朝3時半くらいから東の空を見るのが良いでしょう。
そもそも土星の環を発見したのは、イタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイ。
ただし、ガリレオはこれを環だとは思わず、土星は1つではなく、3つの星がoOoのように並んでいると報告。あsssssss
・1612年末ごろには真ん中の星しか見えなくなりました。これは1612-1613年に環が消失したためでしょう。
・1616年には土星の両側に取っ手がついたようになり、耳のように見えたと述べています。
・1626年は環の消失時期と土星が合で見えない時期が近く、観望チャンスが少なかった、というのも不運でした。
しかし、その後も観測を続けたガリレオは、ますます奇妙な姿を目撃し、大いに悩むことになります。結局こうした変化を説明することはできませんでした。
ガリレオの報告から数えて3度目=土星の公転1周にあたる1642年の消失期は好条件で、観測数が飛躍的に伸びました。同時に、奇妙な見え方を説明しようという動きも活発化していったようです。
そして迎えた1655-1656年の消失で、オランダのクリスティアーン・ホイヘンスが「環」という概念にたどり着きました。
ホイヘンスは、1656年にアナグラム形式で予告をしたのち、1659年の『Systema Saturnium』にて、土星が「黄道に対して傾きを持ち、どこにもくっついていない、薄くて平らな環に囲まれている」ためにそう見える、ということを示しました (Internet Archive )。
1642年の消失期は好条件で、観測数が飛躍的に伸びました。同時に、奇妙な見え方を説明しようという動きも活発化していったようです。
望遠鏡の性能向上も要因の一つと思われます。ただし、ホイヘンスが1655年3月の観測に用いた望遠鏡は改良前のもので、雑なスケッチが残る程度です。ホイヘンスの望遠鏡が特別優れていたから環に気づけた、という訳では必ずしもないようです。
環の厚さや黄道に対する傾きなど、その後も論争は続きます。
しかし、以降の消失をきちんと予測できたことで、環による説明は定着していきました。
ホイヘンスは衛星タイタンも発見しており、2005年にタイタンに着陸したプローブの名前にもなっています。
土星の輪を見るためには、小さくても天体望遠鏡が必要です。
今年最初の天体望遠鏡作りワークショップが逗子の黒門で開催します。
4月29日(祝/火)、14:30~16:30 望遠鏡キット代込みで、5500円。
定員は10名です。詳細は、宙の学校HPか、宙の学校 | Peatix
「15年に一度の『土星の環の消失』を確認するために、天体望遠鏡を作ろう!」の会です。
★晋道も以前参加しましたが、ご家族と一緒なら小学生でも大丈夫です。My望遠鏡素敵ですよ❣