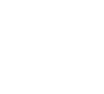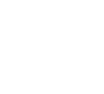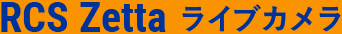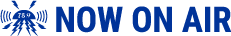2025-5-9 金
SSF Explorer 第58回 5月9日(5/18三浦道寸祭り「笠懸」)
今日のSSF Explorerは5月18日に油壷荒井浜で開催される三浦道寸祭り「笠懸」について公益社団法人第日本弓馬会武田流 教場長の瀬端祐也さんにお話を伺いました。
実は、瀬端さんはとてもお忙しい方なのですが、今日はスタジオにいらしてくださいました。

公益社団法人大日本弓馬会武田流の皆さんは、大阪・関西万博のテストラン期間の4/5(土)6(日)の2日間EXPOアリーナまつり会場で、文化庁との共催で「2025年日本国際博覧会安全祈願奉納流鏑馬・笠懸」を行いました。


 (2025年日本国際博覧会安全祈願奉納流鏑馬・笠懸)
(2025年日本国際博覧会安全祈願奉納流鏑馬・笠懸)
日本の伝統武芸である流鏑馬・笠懸を2日で4回ご披露した他、大鎧の着付け見学、大鎧による騎射、馬へのエサやり体験。展示ブースも鎌倉彫や弓、木馬の体験など多くの方で賑わいました。
この模様はYouTube動画でご覧いただけます。www.yabusame.or.jp
流鏑馬は「祈り」です。大阪・関西万博の安全と成功をお祈りして行ったものです。
数年前の東京五輪・パラリンピックも明治神宮で安全祈願流鏑馬を行っています。
さて、皆さんは「笠懸(かさがけ)」をご存知ですか?
流鏑馬と同じ馬に乗って弓を射るのですが、難易度が非常に高く、殆ど行われていない日本の伝統武芸で、関東ではこの三浦道寸祭り「笠懸」のみす。
(関西では10月第3日曜日に京都上賀茂神社で神事として行われます。)
その名の通り、被っている笠を的にして練習をしたのが起こりです。
流鏑馬の練習や余興として行われていました。
さて、武田流の皆さんは男性も女性もいらっしゃいます。
全ての門人さんが流鏑馬の経験者という訳ではなく、馬も弓も未経験で、入門してからお稽古して初陣(初めてご観覧の方の前でご披露する事)を迎える方も沢山いらっしゃいます。
良く、流鏑馬を仕事としてやっていると思われる方も多いのですが、そうではなく、皆さんお仕事を持ちながら、御殿場の馬場を中心に毎週日曜日お稽古していらっしゃいます。
市役所の職員さんであったり、神社の神職さんであったり、会社の経営者であったり、フラメンコの先生だったり、色々な職業の方がいらっしゃいますが、どの方も流鏑馬への熱意を持っている方々です。
800年続いてきた伝統を守っていくのは簡単にできる事では有りませんね。
◆三浦道寸祭り「笠懸」
日時:5月18日日曜日 小雨決行。
午前11時から三浦一族供養祭、
午前11時45分から神事~矢代ぶり~行軍
アクセス:京急久里浜線「三崎口」駅より京急バス「油壷」行終点下車徒歩7分
若しくは「屋志倉」行「シーボニア入り口」下車徒歩15分
(油壷マリンパークなどの閉鎖に伴いバスの本数が少なくなっていますのでご注意ください)
近隣に有料駐車場も有ります。
荒井浜へ向かう道には三浦一族の旗飾りが(2022年5月撮影)

馬場は弓なりになっていて難易度の高い「笠懸」を更に難しくしています。(2022年5月撮影)

午前中の馬場慣らし(リハーサル)(2022年5月撮影)

観覧席は大賑わい。観覧無料です。
お天気が良い場合は熱中症対策も忘れずに!(2022年5月撮影)

会場となる荒井浜は水が澄んでいる美しい浜。
三浦道寸、荒次郎親子の居城が有りましたが、北條氏に滅ばされてしまいます。
3年間籠城した「新井城」は三浦半島最強の城と言われており、この城跡が毎年公開になっています。
三浦一族のお家芸と言われる「笠懸」。
鎌倉時代の歴史書「東鑑」にも三浦・三崎で源頼朝の前で和田義盛らが笠懸を披露したと書かれています。
歴史絵巻の様なイベントです。
笠懸終了後は射手(装束を付け、馬に乗って弓を射る人)や馬と写真を撮影したり、お話したりする事も出来ます。