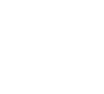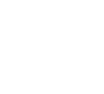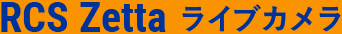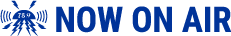2025-7-11 金
SSF Explorer 第67回 7月11日(池子の森緑地エリアの歴史)
◆ライフセーバー電話インタビュー:逗子海岸、逗子サーフライフセービングクラブ副監視長の梅澤倫太郎さん。
昨日の雨で今日は気温が下がりましたが、午後からの日差しに誘われて海岸には沢山の方がいらしています。
リスナーさんのma-yaさんが、先週土曜日、波に足をさらわれて転倒し、左のビーチサンダルが行方不明。向う脛に傷を負いましたが、ライフセーバーさんがビーチサンダルを見つけてくださり、ケガの手当てをしてくださったと番組中Xにポストが有りました。
梅澤さんにご報告したところ、何と!梅澤さんがご対応くださったようです。
ありがとうございます。波の力は侮れないですね。
梅澤さん:波の力は侮れませんが、慣れれば楽しい見方に変わります。
★逗子海岸では子供用ライフジャケット無料貸出していますので、是非ご利用ください。
通常の監視業務は17時までですが、それ以降も夕練しているので、何かあったら声をかけてくださいとの事でした。
◆「池子の森のお話」7月11日と25日は2回にわたって、「池子の森緑地エリアの歴史」です。
緑地エリアに田園風景が有って、集落が有ったことをご存知ですか?
池子の森緑地エリアに住んでいらした方の子孫で語り部の鈴木利幸さんにお話を伺いました。

★今年の夏は戦後80年 戦争の記憶を持つ世代が高齢になってきていますよね。
自ら声を上げることは有りませんが市内には戦争にまつわる痕跡が今も残っています。
本日お話しします池子の森自然公園 緑地エリアは
太平洋戦争の為、S16(1941)年晩秋に7月の通告から僅か4カ月で先祖伝来の地を追われた家族が住んでいた『かしゃばら』集落の跡なのです。
集落の人たちはその年の暮れに真珠湾攻撃と太平洋戦争開戦が知らされ、立退きが当時の時代背景的に抗えないものであったことを痛感したものと思います。
『かしゃばら』とは集落の名前ですが、漢字で書きますと「木」偏に「白」の【柏】と「原っぱ」の【原】現代読みなら『カシワバラ』です。
緑地エリアは9年前に週末に市民開放され、ビジターセンターに集落に関する資料展示がありますが、昨年久木側ゲート付近にプレートが設置されたものの、この地に人々の暮らしがあったことをご存知無い方が多いと思います。
皆さんは「久木」の隣に「池子」の名がつくと地域があるのが当たり前ですが、かつて『かしゃばら』があったことを知る我々などは、「この谷戸は池子ではないんだけどな」と思って足を運んでいるのです。
★とは言え、鈴木さんは戦争の時代をご存知の世代ではないですよね?
私はS47年生まれ53歳 聖和幼稚園、久小、久中、逗子高 都内の大学まで逗子から通っておりました。
大学卒業後は転勤族となり全国津々浦々 北は北海道から南は九州まで7都道府県 転居10回
6年前に家族は逗子に戻しましたが、単身赴任3ヶ所8年目で現在は岡山におります。
★岡山からお越しくださいました。
昔から歴史好き 調べごとが好きな性分ではありますが、
2年前に柏原に暮らしていた我が家の歴史をお話しする機会があり、その際に改めて記録と記憶を整理しました。
大学卒業するまで 集落の最後を知る祖母と23年間暮らしておりましたので、当時は塀フェンスに遮られ こちら側からしか眺められなかった『かしゃばら』の事を、好むと好まざるとに関わらず耳にしていたのですが 図らずも歴史を口伝された者となった訳です。
コレまで要請があれば叔父が語り部として機会がある度に集落のことをお話ししてきましたが、今年90歳となった叔父に代わり、今後は歴史の語り部となるつもりでおります。
★本日と7月25日の2回に分けて柏原についてお話しを伺います。
池子の森からも縄文時代や弥生時代の人々が暮らした痕跡が見つかっておりますし、4・5世紀の古墳時代の多数の横穴が久木でも確認されており、かなり古い時代からこの周辺に人が暮らしていたことは明らかです。
今から84年前 1941.11末に祖父母等の世代が集落を離れる以前、
恐らく今から600年ほど前には柏原の住人として人々が生活していた記録が残っていますが、
その時点で「柏原」の漢字二文字で記されており、名前の由来は分かりません。
我が家でも、昭和60年頃に集落の記憶を編纂した本の出版時にもその由来を明確に伝え聞く方は、いらっしゃらなかったようです
鎌倉時代には源頼朝や北条政子が久木の岩殿寺に詣でていた記録も有りますが、
現在のところ【柏原】の二文字が記された記録として最も古いものと思われるのは
15世紀 南北朝時代 長享3(1489)年4月25日 の日付で、当時下総国 古河で関東を支配していた古河公方[コガクボウ]という役職だった足利政氏が押印している資料です。
足利市渋垂[シブタレ]を起源とされる渋垂小四郎に対する領地の目録案に
『久野谷郷内 猿江村 并(アワセ) 柏原在家』と記されています。
次に書物に登場するのは16世紀 戦国時代 北条早雲を祖とする後北条家3代 北条氏康の時代です。
NHK大河『鎌倉殿の十三人』で描かれていた北条家と区別するために後北条氏と呼ばれています。
北条氏康が永禄2(1559)年に作らせた一族・家臣の地位・役割・知行など記した帳面に
三浦に住む家臣 石上彌太郎 に柏原を所領とする記録があります。
氏康の孫の氏直(うじなお) 初代 北条早雲から数えること5代目で豊臣秀吉の小田原攻めで滅びます。そして江戸時代 徳川家康が関東入府後に関東地方が検知され始めます。
文禄3(1594)年に実施の文禄検地で三浦半島を隈なく検地した記録 相州 三浦郡 久野谷郷 御縄打水帳には、久野谷で9月3日に名主松岡家近くの現在の久木3丁目と5丁目にまたがる壱町田で検地が始まり、北に向かい、柏原の谷戸へと検地が進んだ記録有ります。
徳川家康はNHK大河『どうする家康』でも描かれれていた通り、生まれは三河の松平家です。
桶狭間の戦いから逃れ 岡崎の松平家の菩提寺 浄土宗の大樹寺(だいじゅじ)で厭離穢土欣求浄土という、浄土宗の思想を 授けられ、のちには戦の旗印として掲げ その後 ご存じの通り江戸幕府を開きます。
江戸幕府初期には関東でも浄土宗の寺院を保護し、18か所の僧侶養成する寺を定めます。
この辺り 相模の国では鎌倉 光明寺が唯一の寺院であり、18寺院の1番目に定められていました。
家康が増上寺を菩提寺にしたことで次第に地位はとって代わられましたが、
当然、幕府の庇護を受ける光明寺には最盛期には八十を超える建物があったと言われ、修行する僧と寺の維持や運営の為にはかなりの寺領を与えられていた模様です。
鎌倉一中から下る道から見える大きな宝篋印塔が並ぶ一角が有るをご存じでしょうか?
あの区画は徳川幕府の譜代大名で福島の磐城や宮崎の延岡の藩主を務めた内藤氏の墓地なんです。
内藤家は明暦の大火の後 万治2(1659)年に光明寺に寺領を寄進し菩提寺であった江戸の霊厳寺から、墓所を移し、今に至ります。
その17年後 徳川将軍4代 徳川家綱の時代 延宝3(1676)年12月に幕府 勘定奉行7名の連名で現在の久木…当時は久野谷と呼ばれていた領地を治めていた三浦領 走水番所、大岡次郎兵衛直成(なおなり)に命じ、久野谷452石余りから100石を鎌倉 光明寺に寄進するよう出された幕府勘定役人打渡状 書状が残っています。
命に従い、久野谷の名主と年寄7名が久野谷の全石高452石余りから約2割に当たる100石相当を区分け、翌年の延宝3(1676)年1月には年貢打渡状 で光明寺に寄進されたのが柏原であり、現在の緑地エリアに当る一帯のことになります。
一石とは俵に換算すると2.5俵分 1俵が60kgですので約150kgの収穫量が見込める広さ。
古くから日本の土地面積を表す単位として用いられます「反」は一石を収穫できる水田の面積として用いられていました。
因みに一石は成人1人が1食1合、1日3合程度として1年間で消費する量にと言われています。
ご想像の通り柏原が有った現在の緑地エリアで250俵…つまり15tの収穫量がある訳がないと皆さんも容易に想像できるのではないでしょうか?
久野屋の人々が柏原の田畑全てが豊作で最大収量であったとして、「もしかしたら100石になるかも」と、今でいう「鉛筆をなめて」100石高の体裁を整え 分割エリアを決めたのではないかと想像します。
それ以来、柏原は明治4(1871)年4月13日まで193年間もの間 かまくら光明寺の寺領だったのです。
お聞きの皆様に柏原の事を知って頂く事が出来たら幸いです。
番組へのご感想や本日ご紹介しました柏原にまつわるコメントなどお寄せいただければ幸いです。と鈴木さん。
今日の続きは7月25日にお送りします。
また、9月には昭和初期から立退きを経て現代までをお話し頂く予定です。
★なお、本日エンディングに「池子の森が米軍から返還」というトークが有りましたが、全て返還された訳では有りません。
正しくは、「一部返還」です。訂正と共にお詫び申し上げます。

池子の森の大きな地図もお持ちくださいました。
鈴木さん貴重なお話をありがとうございます。