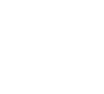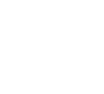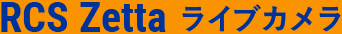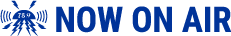2025-7-25 金
SSF Explorer 第69回 7月25日(池子の森緑地エリアの歴史)
◆ライフセーバー電話インタビュー:逗子海岸、逗子サーフライフセービングクラブ
◆「池子の森のお話」7月11日と25日は2回にわたって、「池子の森緑地エリアの歴史」です。
緑地エリアに田園風景が有って、集落が有ったことをご存知ですか?
池子の森緑地エリアに住んでいらした方の子孫で語り部の鈴木利幸さんにお話を伺いました。

★今年の夏は戦後80年 戦争の記憶を持つ世代が高齢になってきていますよね。
自ら声を上げることは有りませんが市内には戦争にまつわる痕跡が今も残っています。
本日お話しします池子の森自然公園 緑地エリアは
太平洋戦争の為、S16(1941)年晩秋に7月の通告から僅か4カ月で先祖伝来の地を追われた家族が住んでいた『かしゃばら』集落の跡なのです。
集落の人たちはその年の暮れに真珠湾攻撃と太平洋戦争開戦が知らされ、立退きが当時の時代背景的に抗えないものであったことを痛感したものと思います。
『かしゃばら』とは集落の名前ですが、漢字で書きますと「木」偏に「白」の【柏】と「原っぱ」の【原】現代読みなら『カシワバラ』です。

(逗子駅近くの和菓子屋さん三盛楼さんの「柏原」。抹茶と小豆のハーモニー!
柏原に住んでいらした飯田さんが先代のご主人の同級生で作られたそうです)
緑地エリアは9年前に週末に市民開放され、ビジターセンターに集落に関する資料展示がありますが、昨年久木側ゲート付近にプレートが設置されたものの、この地に人々の暮らしがあったことをご存知無い方が多いと思います。
皆さんは「久木」の隣に「池子」の名がつくと地域があるのが当たり前ですが、かつて『かしゃばら』があったことを知る我々などは、「この谷戸は池子ではないんだけどな」と思って足を運んでいるのです。
★とは言え、鈴木さんは戦争の時代をご存知の世代ではないですよね?
私はS47年生まれ53歳 聖和幼稚園、久小、久中、逗子高 都内の大学まで逗子から通っておりました。
大学卒業後は転勤族となり全国津々浦々 北は北海道から南は九州まで7都道府県 転居10回
6年前に家族は逗子に戻しましたが、単身赴任3ヶ所8年目で現在は岡山におります。
★岡山からお越しくださいました。
昔から歴史好き 調べごとが好きな性分ではありますが、
2年前に柏原に暮らしていた我が家の歴史をお話しする機会があり、その際に改めて記録と記憶を整理しました。
大学卒業するまで 集落の最後を知る祖母と23年間暮らしておりましたので、当時は塀フェンスに遮られ こちら側からしか眺められなかった『かしゃばら』の事を、好むと好まざるとに関わらず耳にしていたのですが 図らずも歴史を口伝された者となった訳です。
コレまで要請があれば叔父が語り部として機会がある度に集落のことをお話ししてきましたが、今年90歳となった叔父に代わり、今後は歴史の語り部となるつもりでおります。
★7月11日と7月25日の2回に分けて柏原についてお話しを伺いました。
前回、柏原は193年もの間、鎌倉光明寺の寺領であったところまで伺いました。
因みに池子も寛永年間(1640)年頃から幕末の文久3(1863)年まで約220年間
鎌倉 英勝寺の寺領となっていました。
太平洋戦争の時期に弾薬庫建設地となった両地区が江戸時代から近代まで共に鎌倉の寺領であったという共通項があったとは因縁めいた気がします。
なお、幕府領だった小坪を除き 逗子・山の根・沼間・桜山 そして柏原を分村した久野谷は寺領となってしまった柏原と池子と対照的に江戸の中期から江戸湾の海防を命じられた様々な藩の領地となり、特に幕末の56年間は短期間に領主が7回も移り変わる目まぐるしさでした。
当時の柏原や久野谷の写真など残っているわけも有りませんが、
光明寺に柏原が寄進されてから約100年経った寛政5(1793)年の久野屋の風景が残されています。

その時代は現在放映中のNHK大河『べらぼう』で渡辺謙が演じる田沼意次が失脚し、寺田心が演じた田安家から白河藩に養子に出され、11代将軍徳川家斉(いえなり)の時代に老中となる松平定信が寛政の改革を進めた時代です。
前年にはロシアの使節 ラクスマンが大黒屋光太夫を根室に送り届けつつ交易を持ちかけてきましたし、度重なる漂着船や異国船の出没に江戸湾の防備を堅固にしようと勘定奉行たちが伊豆半島から房総半島までを実地踏査したことが有りました。
その際に絵師の谷文晁が同行し各地の景色や旧跡を描いた『公余探勝図巻』を残しています。その中に鎌倉 由比ガ浜から金沢八景に至る道中で【久野谷】と【鐙摺浜】の2枚の写生が書かれたようです。
現在その【久野谷】と【鐙摺】の絵が逗子市役所1階のタイル壁面に複製画で掲示され見ることが出来るをご存じでしょうか?
 (現在未病コーナーの後ろ側になってしまっていてわかり辛いのですが、見えます!写真は斜めになってしまいましたが…お許しください)
(現在未病コーナーの後ろ側になってしまっていてわかり辛いのですが、見えます!写真は斜めになってしまいましたが…お許しください)
【久野谷】として写生された位置は久木4丁目の7-11辺りから葉山方面を望む光景に思われます。見渡す限りの田圃が広がっていたことが伺い知れます。
柏原集落が分村して以来、約265年 昭和16年に柏原を去る際には12軒の家族が生活していました。
集落の入口から谷戸の奥に向かい平地の田畑を避け山裾に沿い6戸ずつ点在していました。
入り口側の6軒を下組、奥の6軒を上組と称し隣組を作り、各組で冠婚葬祭や出産や病時など各組同士で助け合う暮らしをしていました。
苗字は関家3軒、福島家3軒、飯田家3軒、鈴木家3軒 それぞれ苗字が重なる家々を区別するために、屋号で呼び合っておりました
由来は定かではありませんが12軒の菩提寺は久木の妙光寺と鎌倉の本覚寺に分かれます。
集落は鎌倉の浄土宗 光明寺の寺領でありながら、住人の菩提寺は共に日蓮宗という点も謎です。
移転直前まで代々続いてきた集落の暮らしぶりはと言いますと。
かつて大工だったと伝わる家や伝え聞く屋号が示す通り「かじや」「こまもんや」など商工業的なことも片手間で営んでいたと推察される3軒もありますが、ほとんどの家は集落の北にある ため池“大池”や谷戸から流れ出る水で日当たりの良い平野部は全て田畑にしており、全ての屋敷は谷戸や高台に作られておりました。
各戸には井戸があり、夏でも冷たい井戸水は冷蔵庫代わりになったようです。
電気が使えるようになったのは1921(大正10)年で、当初は現在の久木2丁目に変電所があったそうですが、送電設備の発展で廃止になったとのこと。
田畑の中に電柱が立てられ、各戸に電灯が灯るようになったのは逗子で一番遅かったそうで、それまでは菜種油の灯明かランプ、提灯を使っていたそうです。
萱ぶき屋根の平屋が殆どで、柏原集落内や久野谷の萱場で葺き替え用の萱を蓄え,順番に葺き替えを行い、瓦葺は少なく二階建ては2軒ほど。
それぞれ馬や牛、鶏などを飼育している家もあったようです。
田での収量から取り置く自家用(百姓持分)の米を大切に貯め、古米から順に使って暮らしていたようです。
近代以降では米以外に逗子の市場に畑で出来た自家消費以外の作物を売りに出したり、 山から切り出した薪を販売することなどで現金収入を得ていました。
今回は昭和の初めまでのお話しを伺いました。
お聞きの皆様に柏原の事を知って頂く事が出来たら幸いです。と鈴木さん。
番組へのご感想や本日ご紹介しました柏原にまつわるコメントなどお寄せいただければ幸いです。
9月には昭和初期から立退きを経て現代までをお話し頂く予定です。