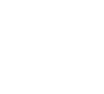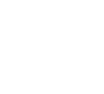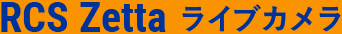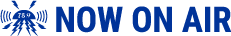2025-7-18 金
SSF Explorer 第68回 7月18日(星空リビング)
◆ライフセーバー電話インタビュー:今日は長者ヶ崎海岸から葉山ライフセービングクラブ理事長の加藤智美さんにお話を伺いました。
長者ヶ崎海岸は駐車場も近く、穴場的な海岸です。一度訪れると再来なさる方が多いそうです。
そして、今年もイベント「ライフセーバーと遊ぼう!」が有ります。
7月27日(日) 長者ヶ崎海岸海水浴場…まだ間に合います!(森戸と一色は満員締切)
葉山ライフセービングクラブのwebサイトから詳細をご覧ください。
◆「星空リビング」プラネタリウムプランナーかわいじゅんこ先生

皆さんは、「野尻抱影」という人をご存じでしょうか?
星の文人とも呼ばれた、英文学者で随筆家。
昭和のはじめ頃に、難しい天文書しかかなかった時代に、一般に人にわかりやすく星のことを語る人でした。私が古本屋さんで買った『星座神話』という本は、初版が昭和8年でした。洋書の翻訳も数多くあります。しかし、彼を有名にしたのは、星の和名を収集したということでしょうか。
1926年(昭和元年)NHKのラジオ番組「星のロマンス」に出演。人気番組となり、続いて「星の伝説」にも出演されます。そのころ、日本には星に関する伝説や名称など特筆すべき物は無い、という定説に疑問を持ち、この人気番組で情報提供を呼びかけたのです。すると、全国から集まる集まる!!!そして『日本の星』『日本星名辞典』を出版。
望遠鏡の購入 1928年(昭和3年)『宝島』の翻訳の印税で口径10センチの天体望遠鏡を手に入れました。当時初任給が15円の時代に、600円したそうです!
宝島に出てくる大砲の名前が「ロング・トム」なので、この愛機にも「ロング・トム」という愛称を付けたそうです。今回、展示もされていますので、ぜひご覧ください。更に、8月1日2日はこの望遠鏡を使って月を見よう!!!という会があります。大人1000円、小中学生800円で、ピーティックスで販売しています。私も行きたいと思っています。仕事が無ければー
冥王星の名付け親
1930年冥王星が発見され、「Pluto」と名付けられました。では、日本では???
和名を冥王星と野尻抱影が提案したのです。現在も中国や東アジアでは冥王星が共通となっています。
では、他の惑星はどうやってなづけられたのでしょうか???
水星や金星という五惑星の名前はギリシャ神話とは関係なく、古代中国で考えられた五行説によります。五行説とは、世界を形作る五つの要素を木火土金水とし、これらの要素の変化や組み合わせで自然界や人間社会の現象を説明しようという考えです。そこで、五行説によりなんでも五つに分類することが行われました。方角や季節、色なども五つに分類されています。
古代から知られた五惑星も五行説に都合がよく、要素が割り当てられました。中国名で辰星(しんせい・たちみぼし)と呼ばれる水星は太陽のまわりをめまぐるしく動くので水の要素の星。太白(たいはく)ともよぶ金星は明るく白く光るので金の要素。螢惑(けいこく)ともよぶ火星は赤い色の火の要素。木星と土星は、よりくすんだ黄色の方が土の要素の土星。残った木の要素を木星に割り当てました。木星はまた中国名では歳星(さいせい)、土星は鎮星(ちんせい)ともよびます。
天王星・海王星・冥王星の三つはローマ神話の神々の名前を訳したものです。
プラネタリウムの解説
渋谷にあった、五島プラネタリウムでの解説もされていました。
時間があれば、ぜひ!45分間の映像もあるので、余裕を持って行かれることをおすすめします。期間は8月31日までです。
8月30日(土)は、「月と日本酒の会」です。旧暦の七夕を皆さんと楽しむ会。キャッシュオンの日本酒は今回七夕にちなんだお酒を3種類ご用意します!