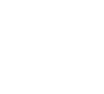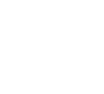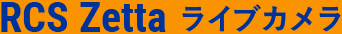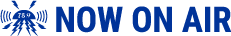2025-8-15 金
SSF Explorer 第72回 8月15日(星空リビング)
◆ライフセーバー電話インタビュー:葉山ライフセービングクラブ理事の加藤智美さん。
今日はお盆休みもあってか海岸が混みあっていましたが、3時を過ぎて少し人は少なくなっています。
今日は、お盆過ぎから増えてくる「クラゲ」についてお話を伺いました。
クラゲに刺されたら…先ずは海から上がって休みましょう。
クラゲに刺されると、痛い~痒くなります。
クラゲの毒はタンパク質なので、先ずは集めのシャワーなどで温めて、落ち着いてきたらその後、冷やします。
海岸の砂などという情報も有りますが、これは間違ったものです。
クラゲ(アンドンクラゲなど)が増えてきています。海に入るときには、ラッシュガードなど長袖長ズボンで、素肌の露出を少なくしましょう。
クラゲに刺された際の対象方法(公)日本ライフセービング協会のクラゲに刺されたらをご参照ください。
◆「星空リビング」プラネタリウムプランナーかわいじゅんこ先生。
今日は岡山から電話インタビュー。
ペルセウス座流星群は、ご覧になりましたか?
私は、美星町のキャンプ場で、ペルセウス座流星群をみよう!というイベントをやってきました。ここ数日、ずっと天気が悪くて、一番の見頃と言われていた、8月12日から13日の朝にかけても、雲に覆われていました。でも、13日は晴れて、暑くて・・・あとは、キャンプ場の乾きがチョット心配なくらいで。夕方になると、少し雲行きが怪しく、ザッと雨が降りそうな予報もありましたが、なんとか雨は降らず。でも雲が少し厚めにでてきました。
はじめは、スクリーンを使ってのお話しだったので、なんとか。そして、45分くらいすると、ポツポツ!あわてて、機材などを屋根のあるところへ避難させて、しばらく待ちました。結局、コットを出して、曇り空をながめていましたが、だんだんとところどころ意晴れ間が見えて星が!それぞれ、みなさん寝転んで、思い思いに夜空を見あげていました。結局、私は12時過ぎくらまで見ていましたが、寒くて・・・!
今回は、テントも張りましたので、せっかくなんで、テントに潜り込み寝ました。4時くらいにトイレに行ったとき、東の空に金星も木星をみて、満足して、また寝まし(笑)結局見た流れ星の数は10個くらい。
でも、いろいろな参加者の方々と楽しかったです!
そして、昨日のニュースでは、青森の弘前天文台で、流れ星のクラスターが撮影され話題になっていますね。
これは「流星クラスター」と呼ばれる珍しい現象で、流星物質が地球大気に突入する少し前に、何らかの原因で細かい破片に分裂し発生するものと考えられています。1997年のしし座流星群の際に初めて観測され、その後も、わずか数例しか報告されていないという超レアな現象といえるでしょう。
ハワイのマウナケアでも撮影されています。こんなの直で見たら、驚いて子wも出ないかもしれない!!と思いました。まだ、ご覧になっていない方は、ぜひ、映像を検索して見てください。
そして、そろそろ夏休みも後半。子ども達は、宿題が気になる時期でしょうか?
星空観察も楽しいのですが、読書感想文の題材に、宮沢賢治はいかがでしょう?というか、大人の方にもオススメです。
実は、この秋に宮沢賢治をテーマのプラネタリウム企画がありまして、また、本をめくっている所なのです。『銀河鉄道の夜』だけではなく、いろいろなお話しに宮沢賢治の宇宙観がでています。
有名な「星めぐりの歌」は、『双子の星』の中に出てきます。
双子の星は、ふたご座ではありません。
「天の川の西の岸にすぎなの胞子ほどの小さな二つの星・・・」とあります。新潟大学の宇宙物理学者で、宮沢賢治研究でもある、斉藤文一先生が書かれた文章に、「星の胞子と呼ばれているものがある」と。それは、星間空間で星が誕生する前の重力収縮直前の段階との天体と考えられています。
周囲がくっきりと丸く、まるで、水滴のように美しい、高密度の星間物質のかたまりで、小球体の意味の「グロビュール」と名付けられているものがあるのです。
2002年、NASA の HST(ハッブル宇宙望遠鏡)が撮影した、「サッカレーのグロビュール」と呼ばれる暗い天体の写真が公開されました。そのときの記事を掲載します。
IC 2944 中の「サッカレーのグロビュール」
AstroArts 天文ニュース【2002 年 1 月 7 日 STScI Press Release】

IC 2944 とその中の「サッカレーのグロビュール」(写真提供:NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)、謝辞:Bo Reipurth (University of Hawaii))
この天体は 1950 年に天文学者 A.D. Thackeray によって発見された。周囲に見える赤いところは星形成領域 IC 2944 で、5900 光年彼方のケンタウルス座の方向にある。グロビュール(小球、胞子)という、高密度の暗く不透明な雲の起源や性質については、今のところほとんどわかっていない。ただ、どうやら HII 領域(電離水素領域)と呼ばれる大きな星形成領域と関連がありそうだということだけはわかっている。
写真中で右上に見える大きなグロビュールは、実際は 2 つのものが重なって見えている。それぞれの大きさは長い方向でおよそ 1.4 光年で、2 つ合わせた質量は太陽の 15 倍以上である。周りを取り囲んでいる HII 領域 IC 2944 はガスやチリに満たされており、太陽よりもはるかに高温で質量の大きい O 型の星の集団によって照らされ、熱せられている。
ハッブル望遠鏡の高い分解能のおかげで、これらグロビュールの複雑な構造を調べられるようになった。観測の結果、どうやらグロビュールは激しく破壊されているらしいということがわかってきた。おそらくは O 型星から放射されている強い紫外線によるものだと考えられている。
ガスやチリの濃い塊であるグロビュールは O 型星が誕生する以前から存在しており、もし O 型星の誕生が遅ければ、収縮して太陽のような低質量の星々になったのだろう。しかし、O 型星が誕生してしまったために、グロビュールの周りの低密度部分を剥がされて存在をあらわにされただけでなく、さらに紫外線を浴びてバラバラに壊されてしまうという過酷な運命になってしまったようである。
双子の星は、ポンセ童子とチュンセ童子。小さな水晶のお宮に住んでいます。お日様が沈んで、また昇るまで、二人は向かい合って一晩銀笛を吹くのです。
お話しは二つありますが、一つ目の最後に「星めぐりの歌」が出てきます。
あかいめだまの さそり
ひろげた鷲の つばさ
まさに、夏の星座ですね。今頃だと20時くらいの南の空低いところにさそり座、そこから左上に向かっていくとわし座が見えています。目印は明るい一等星アルタイルの両脇に小さな星があるところです。
そこから、くるりと北の方角を向くと
あおいめだまの 小いぬ
ひかりのへびの とぐろ
こいぬ座は、尻尾の先が北極星なので、いつでも見えています。この時間はこぐまが逆さまになっていますが、体は、北極星の西側、左上にあります。
そして、へびのとぐろ、ですが、星座にはうみへび座、へび座といろい
うみへび座も頭の近くがクルッと回っています、へび座はへびつかい座に捕まれているのですが、尻尾の辺りがクルッと回っています。そして、こいぬ座にくっつくかんじでいるのが、りゅう座です。へびではありませんが、これがあちこちグルグルとぐろを巻いています!おそらく、へびは、このりゅう座だろうというのが多くの見解ですね。りゅう座は、こぐまと一緒に、北極星の周りを回っているのです。
オリオンは高く うたい
つゆとしもとを おとす
この時期、明け方の東の空にオリオンが昇ってきます。ペルセウス座流星群の観測の時もそうでしたが、昼と夜の寒暖差があったので夜露がすごかったのです。 さすがに霜はありませんが。
アンドロメダの くもは
さかなのくちの かたち
おおぐまのあしを きたに
五つのばした ところ
小熊のひたいの うえは
そらのめぐりの めあて
オリオンが昇る前の20時の空には実は、アンドロメダ座も見えています。
アンドロメダ座は、東の低い所に、そしておおぐま座は、脚を北の方角の大地を踏むような姿で見えています。そして、腰から尻尾にかけての北斗七星から5倍延ばした所に北極星があります。
こうやって今の時期の夜空を一晩中眺めると、見ることができますよ。