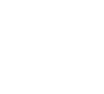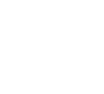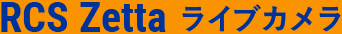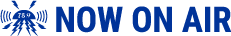2025-8-22 金
SSF Explorer 第73回 8月22日(池子の森のお話)
◆ライフセーバー電話インタビュー:逗子サーフライフセービングクラブ監視長の大森海依さんにお話を伺いました。
今日は雷が鳴ったらどうすればよいか?伺いました。
雷雲が近付いてきたら、危険ですので直ぐに海から上がってください。
ウェットスーツを着ているから大丈夫。という方がいらっしゃいますが、危険です。
海岸では直ぐに放送を流しますので、海から上がってください。
逗子海岸では子供用のライフジャケットを無料で貸出ししています。
週末などは沢山申込みがあります。自分で買わなくても無料で貸していただけるので、利用しない手は有りませんね。また、正しく付けて目を離さないでください。
海開きもあと10日。逗子海岸の逗子サーフライフセービングクラブの皆さんは、笑顔で帰って頂きたいと。
ライフセーバーのステーションのライフセーバーの皆さんにもお声をかけてくださいね。
逗子海岸は今日が最終回。ライフセーバー電話インタビューは来週の葉山ライフセービングクラブ電話インタビューが今年の最終回となります。
◆「池子の森のお話」
今回、6月から7月にかけて、池子の森で哺乳類の調査を行った鎌倉学園 生物部 高校2年で生物部部長の鈴木玲音さん(右)と顧問の山本亮太先生(左) にお越しいただきました。

晋道:生物部はどんな活動をしているんですか?
鈴木さん:普段は、飼育している生き物の世話をメインに活動しています。学校の近くの山で昆虫採集やホタル観察会などのイベントも行っています。
他には夏合宿もあります。
今年は2泊3日で仙台に行きました。1日目は八木山動物園、2日目はHOKUSHU仙台市科学館とうみの杜水族館、3日目は松島巡りの観光船に乗る予定でしたが、津波警報が発令された為、急遽東北大学の博物館と植物園へ訪問しました。
いろいろと活動していますが、基本的に自由度が高く、自分たちで決めて活動しているので、ゆるっとした雰囲気です。
今回は、初めての試みとして、池子の森自然環境調査会が行っている哺乳類調査に参加しました。
晋道:哺乳類は、どんなふうに調べるのですか。調査の方法を教えてください。
鈴木さん:環境省が全国で行っている「モニタリング1000里地調査」というのがあるのですが、池子の森はその調査エリアのひとつで、今回はその調査に参加しました。この調査は、藤沢清流高校生物部といっしょに行いました。
具体的には、赤外線センサー付き自動撮影カメラを使って調査します。池子の森の中に、6月~7月にかけて、環境の異なる場所、森の尾根,川沿い,やぐら(手掘りの横穴)の3地点にカメラを仕掛け、1カ月後にカメラを回収し、どのような哺乳類または鳥類が写っているかを調査しました。
調査の手法については、日本自然保護協会の大野正人さんに指導していただきました。
晋道:1ヶ月間カメラを設置したとのことですが、いったい何枚ぐらい写っていたんでしょう。
鈴木さん:赤外線カメラは、カメラの前を動物が通過するとシャッターが降りる仕組みです。もちろん動物も映っていましたが、草木が風で揺れただけでもシャッターが降りてしまうので、そういうのを含めると1048枚ありました。ものすごい枚数・・・・。
それを何台ものPCを並べて、藤沢清流高校生物部といっしょに総勢15人で分析しました。
晋道:どんな動物が映っていたんですか。
鈴木さん:晋道さんは、どんな哺乳類が写っていたと思いますか?
晋道:以前長者ヶ崎の先に住んでいたのですが、タヌキが親子で来たりしていました。また、アライグマやハクビシン、タイワンリスなどでしょうか?外来生物でしょうか?
鈴木ん:実は画像データを見る前に、自分たちもどんな哺乳類が映っているだろうか、そもそもどんな哺乳類が三浦半島、あるいは神奈川県にいるんだろうと、まずはリストアップしてみたんです。
そのときに出たのが、タヌキ、ハクビシン、コウモリ、タイワンリス、アライグマ、アナグマ、ネズミのなかま、サル、モグラ、イノシシ、シカ、イタチ、キツネ、ムササビ、モモンガなど。
晋道:うわぁ、随分色々な動物がいるのですね。
鈴木さん:このうち、どれぐらいが写っているのか、・・・・・
タヌキが圧倒的に多かったです。他にも、アライグマやハクビシン、タイワンリスが写っていました。中には、1枚の画像でタヌキが3頭一緒に映っているのもあり、家族なのかな、と思われるものもありました。種類はわからなかったのですが、ネズミなどの小動物も見られました。
晋道:けっこうはっきり写るものなのですか?
鈴木さん:動物は動いているので、ぶれているものもあって、しかも夜の画像はモノクロなので見分けがしにくいですね。
晋道:どうやって見分けるのですか。識別ポイントとかあるのかしら。
鈴木さん:はい、たとえば、タヌキだったら丸い顔、アライグマだったら耳の下に白い毛が有る…というような特徴を抑えます。
晋道:写るのは哺乳類だけですか?
鈴木さん:実は、鳥もけっこう写っていました。水路に仕掛けたカメラには、水を飲んだり、水浴びをしにくる鳥もいて、・・・・・。
その中でも一番多かったのが、ガビチョウ。
晋道:ああ、・・・・・ガビチョウも外来ですね。
鈴木さん:シジュウカラやコジュケイなども見られました。
晋道:調査に参加してみて、いかがでしたか?
鈴木さん:写っている時間帯をみると、圧倒的に夜に写っていたものが多かったです。
哺乳類のほとんどが夜行性だということを、あらためて実感しました。
これらは、昼間に見ることができないので、もしかしたらあまりいないのではないかと思いがちですが、・・・・・。
市街地のすぐ近くでもあるにも関わらず、ここまで多くの種を確認できたことに驚きました。
アライグマやネコなどの外来種が思っていたよりも多く写っていて、そこは少し悲しかったです。が、在来の生き物も多く写っていたのでそれは嬉しかったです。
どんな種が生息してまたどれくらいの個体数かなどの動向を調査していくことは、今後の生態系を守っていく上で大切なデータになると思いました。
晋道:生物部顧問の山本先生にもお話を伺います。今回の調査に参加していかがでしたか。
山本先生:私は化学の授業を受け持っているのですが、実験のことなどこのビーチFMの側に有る理科ハウスさんによく伺っていて、今回の池子の森の調査は、理科ハウスの山浦さんとの交流から、やってみませんか?と持ちかけられました。
実際、生徒たちは興味を持つのか?と思ったのですが、5名の生徒が興味を持って、先ずはカメラを設置する場所などの下見に来る事からスタートしました。
実際に写真を分析する段階では「なになに?」と15人の部員たちが加わって、1000枚以上の写真でしたが、1日で分析は終わりました。
また、今回の調査を通じで藤沢清流高校生物部の生徒さんたちとも交流することが出来、とても有意義で山浦さんには感謝しています。
晋道:良い出会いが有って、生徒さんたちにとっても充実した夏休みになったのではないでしょうか。
晋道:鈴木さん、今後やってみたいことはありますか?
鈴木さん:今回の調査は夏でした。秋から冬にかけてはどんな哺乳類が活動しているのか知りたいです。
池子の森での調査も継続しつつ、普段僕らが採集を行っている山にも赤外線カメラを仕掛けると、どのような生き物が写るかを調べてみたいです。
一度だけ(どこで?)フクロウを見たことがあるからもう一度見てみたいです。
晋道:自主的に動いて調査した皆さんの調査の成果は環境省でも前例の無かったことで、話題になっているそうです。
今後の活動が楽しみです。
また、私達のこんなに近くに、多くの生き物が生活している事を知る事が出来ました。
ありがとうございます。