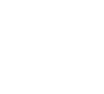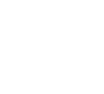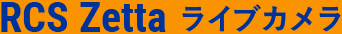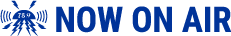2025-11-7 金
SSF Explorer 第84回 11月7日「星空リビング」
「星空リビング」プラネタリウムプランナーかわいじゅんこ先生
いよいよ「立冬」。この頃は、あの猛暑を忘れるような涼しさと寒さですね。
先日は、後の月を愛でる会を開催しましたし、逗子コミュニティーパークで星空案内をして皆さんと月を見上げ、土星を見つけて楽しみました。つい先日、5日は「スーパームーン」と話題になりつつも、曇っててなかなか盛り上がらずにおわりました。地球に対して、楕円軌道の月が近づいたり離れたりしているので、大きさが変わるのです。
スーパームーンは、天文用語ではありません。
元々は、アメリカの占星術師が1979年に使いだして、それが、科学的な記事に取り上げられて、広まったのが2011年くらい。いまではすっかり定着してますね。それで、宙を見上げる人が増えたら嬉しいです!
地球と月の距離は、一番近くて約35万7000キロメートル、一番遠くて40万6000キロメートルです。その差は4万9000キロメートル。地球一周が大体4万キロメートルなので、それが遠いと思うか?それほどでもないと思うか?ですね~
マスコミで、「スーパームーン」と言われて、そうとう大きくなると思われている方もいるようですが、見て違いがわかる人は、いつも月を見上げたり、夜空を楽しんでいる人だと思います。「スーパームーン」だけではなく、いろいろな言葉が氾濫していますので、ただただ、言葉に踊らされることなく、自分でも調べてみて正しい情報で楽しみたいですよね。
ちなみに、月は1年に3センチずつ地球から離れていってますので、月はどんどん小さく見える様になるということです。(もちろん肉眼でのちがいはわからないと思いますよ~、踊らされないでね~)
それから月でもう一つ。
半月を「上弦の月」とか「下弦の月」と呼びますが、あれは沈むに弦の部分が上になるかなるか?下になるか?ということでしたよね?と。小学校の時にそう習った人は多いと思います。私も、そのように習いました。
実は、もう一つあります。
月の形は、新月、満月とその間に半月がありますよね。半月のことを「弦月」と呼びました。弓に張った弦(つる)の形に似ているのでその名前が付いたと言われています。「弓張月」とも呼ばれます。そこで、上弦と下弦のちがいですが、暦を上旬、中旬、下旬区切ると上旬にくる弦月を「上弦の月」、下旬に来る弦月を「下弦の月」と呼んだという説です。
暦が普及する前から、あった言葉なのでは?そうであれば、弦を上向きに沈むの方が良いのでは?とも言われますが、上弦の月は暗い時間に沈みますので、その様子がわかるのですが、下弦の月は明るくなってから沈みますので、弦を下にしてという様子がわかりにくいというか・・・。
月の出を好んだ日本人としては、月の出では?とも思いましたが、これが、上弦の月は明るいうちなので、見つけにくく。弦の向きを考えるのはどうかな?と。
月の名前は、本当に多くて、調べてみるのも楽しいですよ。
それから、11月18日(火)はしし座流星群のピークです。ピークは1日の3時なので、17日の夜から18日の朝にかけてが一番いいでしょうね。天気が良いことを祈りましょう!!!
夜中の3時にしし座は東の空にいます。ですので、その頃から明るくなるまで外衣と思います。結構寒いでしょうね。根性入れて厚着してください。風邪引かないように!
そういえば、「レモン彗星」はどうでしょうか。
日本時間で11月8日22時頃、太陽に接近します。
この日、17:40 西南西の空15度の高さにあります。太陽に近いと言うことは、明るい空で探さないといけないので、大変です。双眼鏡や望遠鏡が必要ですね。
望遠鏡と言えば、天体望遠鏡作りを黒門カルチャーで開催します!
土星の環の消失の前に作ってみよう!というコトでやるのですが、もちろん月のクレーターもバッチリ見える望遠鏡なので、ぜひ、このチャンスにつくりに来てください。詳細は、ピーティックスか、宙の学校のHPで!
11月22日は「秋の夜空の星とピアノ」です。いよいよ近づいてまいりました。
チケットもまあまあ好調のようです。
当日は、本の販売もいたしますので、おたのしみに!!!