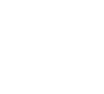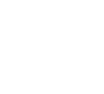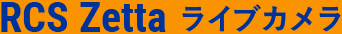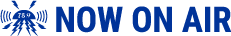2025-10-24 金
SSF Explorer 第82回 10月24日「池子の森のお話」
「池子の森のお話」
今日は「池子の森の水生昆虫について」18日の観察会で講師を務められた小口岳史さんにお話を伺いました。
小口さんは茅ヶ崎生まれの茅ケ崎育ち、2010年に逗子に引っ越されたそうです。

・水生昆虫とは
一生のうちどこかのステージ(卵・幼虫・蛹・成虫)で、水中もしくは水際で生活する昆虫類の総称です。
トンボやホタルのように幼虫は水中生活でも成虫になると陸上生活をするもの、ゲンゴロウやアメンボのように成虫になると地上にも出られるものの基本水中・水辺で生息するもの、一部の水生カメムシ類のように成虫になっても基本的に水から出ないものなどスタイルは様々です。
分類群もトンボ類・カゲロウ類・カワゲラ類・ガ類・ハエ類・コウチュウ類・カメムシ類など多岐に渡ります。
・なぜ水生昆虫をしらべるのか
一口に水生昆虫と言っても、種類それぞれで好みの水環境は異なっています。
そのため水生昆虫を観察していると、その場所の水辺の環境の様々な情報、たとえば水質や水量、岸辺や周辺の環境など、を知ることができるのだそうです。
また、比較的外来種の影響を受けにくく、その地域本来の昆虫類を知ることができるのが特徴です。
・池子の森にはどんな水生昆虫がみられるか
池子の森にある水辺環境は「浅く広めの池」「そこから流れ出す細流」「谷戸奥の湿地」の主に3つがあります。
「池」の主役はなんといってもトンボ類で、シオカラトンボやギンヤンマといったなじみ深い種類に加え、コサナエというトンボが生息しています。コサナエは神奈川県では非常に希少なトンボで、極めて貴重な発生場所となっています。また、アシ原が広がるため、そういった場所を好む希少なアメンボ類なども記録されています。
「細流」ではゲンジボタルが発生しています。ただし、池のすぐ下流では水量が少なく流れがしばしば途切れがちで水温も高く、水生昆虫はあまり多くないとの事。
環境的には「細流」に生息する水生昆虫は、むしろ非開放区域内のより上流部を中心に生息していると考えられます。
「湿地」ではサラサヤンマやスジグロベニボタルといった、湿地ならではの水生昆虫が生息している。もともとこういった湿地は三浦半島には多かったのでしょうけれど、現在その多くは開発され極めて貴重な環境となっています。
・水生昆虫相から見えてくる池子の森の自然
水は全ての生きものにとって必要不可欠であり、水辺環境が多様であればあるほど、その場所の自然も多様で豊かであると考えることができるでしょう。
そういった意味では池子の森には「池」や「湿地」が維持されていることで、三浦半島に残された数少ない自然であると考えることができます。特にコサナエやスジグロベニボタルの生息は極めて貴重なものであり、後世に誇れる環境であるといえます。
一方、「川」としては公園内ではかなり不安定な環境しか残されていませんが、周辺の地形を考えても、当地はもともとあまり「川」の環境に恵まれていなかった可能性が高いです。そういった中でゲンジボタルが生息できる「細流」がかろうじて残されてきたのは、むしろ運が良かったのかもしれません。
水辺は全ての生きものの命のよりどころとなるものであり、水生昆虫はまたその場所の生態系ピラミッドの下層を支える生きものでもあります。水生昆虫相をモニターして、これらが健全に生息できる環境を残していくことで、池子の森全体の環境を健全に保ち続けることができるのではないでしょうか。


 池子の森には色々な形態の水場が有り希少な昆虫が。
池子の森には色々な形態の水場が有り希少な昆虫が。
急に季節が進みましたね。昨日は二十四節季の「霜降」その通りに富士山が初冠雪しました。
そして、今朝、一瞬でしたが虹が出ました。
虹を見ると良い事が有る様な気がして嬉しいです。
今日もお聞きくださいましてありがとうございます。
 10月23日霜降の日、富士山初冠雪。
10月23日霜降の日、富士山初冠雪。
 10月24日、番組の朝、虹が出ました!
10月24日、番組の朝、虹が出ました!